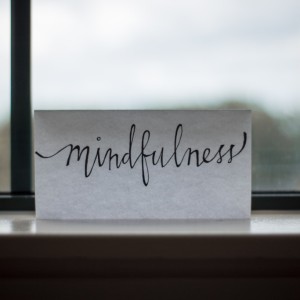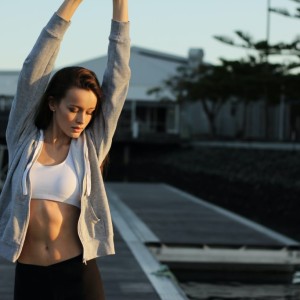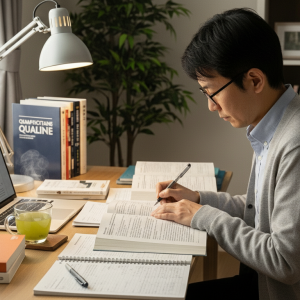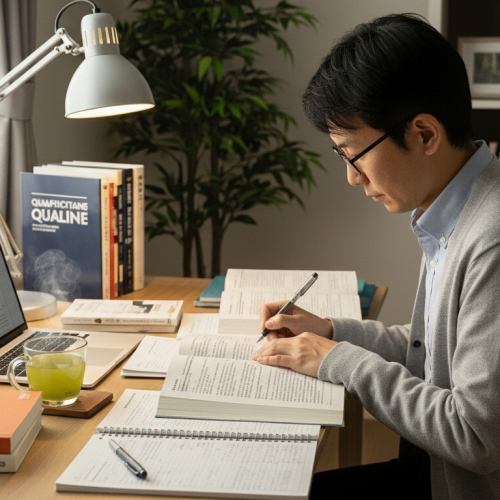Q. 社内リスキリング制度を活用しても、結局“使えるスキル”が身につかないのはなぜですか?

Q. 社内リスキリング制度を活用しても、結局“使えるスキル”が身につかないのはなぜですか?
A. 多くのケースでは、「学ぶ内容が実務と結びついていない」「学習後の活用設計がない」ことが原因とされています。

せっかく社内リスキリング制度を利用しても、実務で活かせるスキルが身につかないのはなぜでしょうか?

McKinseyの調査によると、世界の企業の約87%がスキルギャップを抱えており、そのうち準備が整っているのは約3割にとどまります。こうした背景から、受講完了を目的化した学習制度では実務との接点が弱く、スキル定着につながりにくいケースが指摘されています。

学ぶ内容を現場に結びつけるには、どんな工夫が必要ですか?

リスキリングを成功させるには、①実務課題と連動した学習内容、②学習と業務を往復できる実践環境、③成果の測定とフィードバックの仕組みを整えることが重要です。McKinseyも「学習を業務に埋め込むこと」が成果向上の鍵としています。

オンライン講座を受けるだけでは不十分ということでしょうか?

はい。受講だけでは「知っている状態」で終わる可能性があります。学んだ内容を社内プロジェクトで試すなど、実践を通じて成果を測る設計が必要です。

AIや自動化が進む時代、“使えるスキル”とはどのようなものですか?

世界経済フォーラムによると、2025年までに全労働者の約50%がリスキリングを必要とする見通しです。今後は単純作業よりも、AIと共に考え、課題を定義し、最適な解決策を導くスキルが重視されるでしょう。
🧾 詳細解説
リスキリング制度が効果を発揮しない背景には、「学び」と「実務」の分断があります。McKinseyの調査では、世界の企業の約87%がスキルギャップを抱え、準備が整っているのは約3割にとどまるとされています。これは、制度が「受講完了」をゴールにしており、業務課題と結びつかないことが多いためです。
成功するリスキリングには、①学習テーマを実務課題から逆算して設定する、②学んだ内容をすぐ試せる環境を用意する、③成果を数値化し、フィードバックを繰り返す――この3つの要素が重要とされています。
また、世界経済フォーラムは「2025年までに全労働者の約50%がリスキリングを必要とする」と指摘しています。AIや自動化が進むなかで、単純作業や知識だけではなく、「AIを活用して問題を発見し、解決まで導く力」が今後の競争力の源泉になります。制度を「研修型」から「実践サイクル型」へ再設計することで、“使えるスキル”の定着が促進されます。
📚 出典・参考資料
McKinsey & Company “Beyond Hiring: How Companies Are Reskilling to Address Talent Gaps”
McKinsey & Company “Upskilling and Reskilling Priorities for the Gen AI Era”
World Economic Forum “Organizations Can Get Reskilling Right: This Is How”
World Economic Forum “4 Ways to Reskill the Global Workforce”
本記事は一般的な情報および公表データに基づいて構成しています。実際のリスキリング制度の効果や運用方法は、企業の規模・目的・業種により異なる場合があります。